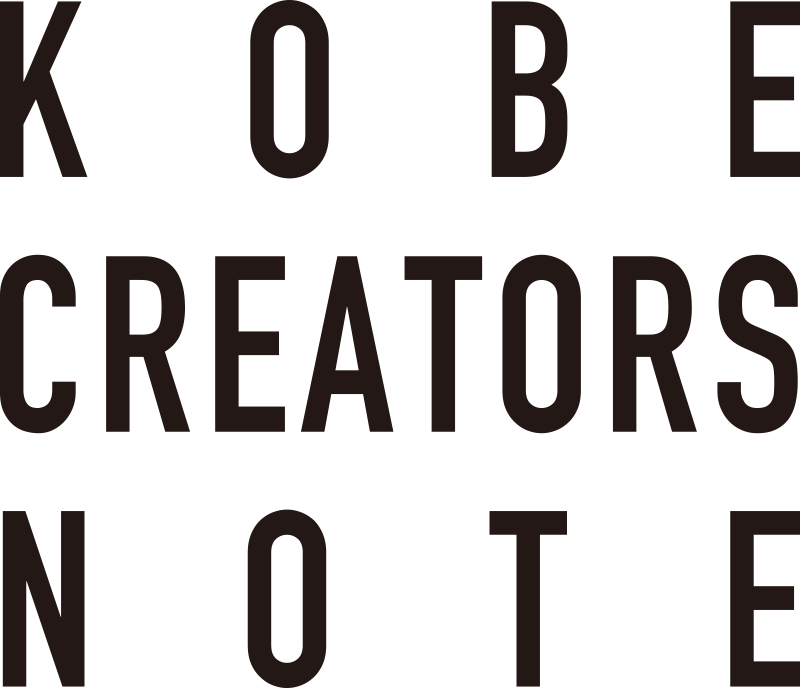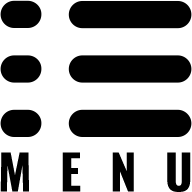
過去のイベント
2020.08.03
【イベントレポート】CROSS2020 vol.2 「クリエイティブにまつわる法-知的財産権」

2020年7月14日、クリエイターやビジネスパーソンにとっての学びの場となるオンライントークイベント 「CROSS2020」vol.2を開催しました。
今回のテーマは「知的財産権」。ゲストはvol.1に引き続き、クリエイティブにまつわる法について神戸セジョン外国法共同事業法律事務所の崔舜記氏です。
「クリエイティブにまつわる法-知的財産権」
知的財産権とは
知的財産とは、価値のある無体物のこと。知的財産が付与された物それ自体は所有権によって守られます。例えば、白紙の紙それ自体は安価で購入することができるが、著名な作家による小説が書かれた紙は、価値のある紙となります。つまりただの物に人の知恵である知的財産(価値)が加わることで財産が構成されるのです。
知的財産法は、法律が何を守るか?によって種類や保護の体系が変わります。(図1参照)

例えば、パソコンにはさまざまな知的財産が含まれています。パソコンについているブランドロゴは商標権によって守られ、パソコンそれ自体が画期的なデザインを持ち形状に価値がある場合は意匠権が、パソコン内部の技術は特許権や実用新案権によって守られています。このように一つのものに対して各法による保護が重なるケースもあります。

今回はその中でも、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権を例に説明しました。
特許法について

特許法とは、知的財産の中でも、技術に関する法律であり、「発明」を保護する法律のこと。(図1参照)「発明」とは、法律上でいうと「自然法則」を利用した「技術的思想」の「創作」のうち「高度なもの」を指します。わかりやすく言うと、新しく作り出したことや作る過程におけるアイデアのうち技術的に高いことを保護する法律だと言えます。
例えば身近なものでいうと「雪見だいふく」が特許を取得しています。「雪見だいふく」はバニラアイスを餅のような生地でコーティングしたロッテ社が販売するアイスクリームですが、本来ならば劣化しやすい餅生地を長期間にわたって食感や風味の劣化をなく維持するために、さまざまな技術が使われていることから、その製造方法が特許を取得しています。
しかし、ここで重要なことが、この特許権は得て「特許権者」になるためには、出願が必要である点です。そしてこの「特許を受ける権利」は発明の「創作者」に帰属します。

また、ここで問題となるのが、会社に属しているものが職務として発明した場合は誰が「特許権者」となるのか。この場合、会社が法人名義で申請している場合、著作権は会社に帰属します。この例として、青色発光ダイオード裁判について話しました。これは青色発光ダイオードの製造に関連する特許をめぐって日亜化学工業株式会社と発明者の間で争われた裁判のこと。この裁判で発明者は、この発明は職務発明ではなく特許を受ける権利を会社に譲渡した事実はないと主張したため、最終的には特許権は会社にあることが認められたが、発明の対価として巨額の補償金が発明者に支払われました。この例であるように、法人にて著作権を申請する場合は、内部での合意も非常に重要です。

つづいて、特許法において特許権者が得られる権利についてです。
特許権を得るためには、出願が必要であり、審査が長期にわたるケースもあります。しかし、出願された発明内容は、1年6ヶ月後には審査中でも公に公開されます。もしこの技術公開により、権利が侵害された場合は、審査中であっても補償金請求権を得ることができます。
また、特許権を取得した場合、発明を独占的に実施できるが、この権利は永続的な物ではなく、出願から20年後には第三者も自由に利用することができます。これは、「権利の保護」と「新たな発明、創作」との調和のためです。
では、特許権を取得するためにはどのような要件を満たす必要があるのか?

特許権を取得するためには特許庁に出願する必要があるが、特許法上の発明にあたるか判断するために、今までにない新しいものか(新規性)、容易に考え出すことはできないか(進歩性)、先に出願されていないか(先願)、などの要件について審査されます。
つづいて、特許権が侵害された場合、どのような救済措置が行われるのかについてです。


特許権は無体物であることから、侵害の発見や損害の立証が困難なため、独自の規定が必要となります。もし特許権が侵害された場合は民事的な救済措置として、現在及び将来における侵害の差し止めを求めることができ、また、過去の侵害による損害賠償請求をすることができます。また、侵害品の廃棄と侵害品の製造装置の廃却を求めることもでき、さらに侵害によって失った信用を回復する措置として、侵害者に対して全国紙への謝罪広告の掲載を求めることもできます。これは侵害者が仮に特許を取得していることを知らなかったとしても過失が推定されるために、侵害者は過失責任を問われることとなるので注意が必要です。
これからのことを踏まえ、特許法について特に重要なポイントをまとめました。

実用新案権について
つづいて実用新案権についてです。

実用新案権は「自然法則を利用した技術的思想の創作」を保護する法律として、特許権と本質的に同じものを保護するが、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とされています。簡単に言うと実用新案権とは特許にまでは至らない技術、ちょっとした発明を保護する法律です。保護の内容や制限など多くが特許権と同様のため、ここでは特許とは違うところを中心に話しました。

実用新案権は特許と同様に、要件を満たした上で申請する必要があります。しかし、実用新案権の場合は、出願された実体的内容の審査は行われず形式的な審査のみで登録されるため、特許よりも早期に簡易に保護できることが多いです。

意匠権について
つづいて意匠権についてです。意匠権とは物品全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザインや、画像のデザイン等物品の特徴的なデザインに対して与えられる権利のことです。

意匠権の保護の対象を巡っては、カップヌードル事件やコネクター接続端子事件を例にしました。カップヌードル事件では日清社が販売する「カップヌードル」の容器に描かれた文字は意匠権の保護対象となるかについて議論されました。この事件では、文字はあくまで伝達手段であって模様ではないため意匠権の保護対象とならないと判断されています。また、コネクター接続端子事件では、肉眼では認識できないほど微小なコネクター接続端子について、視覚性が要件を満たしていないと結論づけられています。このように意匠権の対象となるには、有体物であるかの物品性と、模様や色彩のみではなく形状をもっているかの物品の形態、肉眼での確認が可能かの視覚性を満たす必要があります。

>意匠権は、特許権や実用新案権と同様に申請が必要であり、意匠の「創作者」に「意匠登録を受ける権利」が帰属します。また、登録から20年間は意匠を独占的に利用することができます。

意匠権の出願要件には、工業上の利用可能性が含まれているため、芸術品のように一品製作のものは対象外となるため注意が必要です。また、類似意匠を申請した場合、そのものが類似か否かは、「一般需要者の立場からみた美感」によって判断されます。
また、意匠権の申請はしていないものの、新規で出願された意匠が、すでに既出の意匠と類似している時の注意点についても話しました。

例えば、出願された意匠とは別個独立したもので、出願される以前からすでに創作されており、ネット等で公開されているまたは公開する準備をしていたものがある場合、出願以前に創作された根拠を示すことができれば先使用権として保護の対象になりません。このため、クリエイターにとって創作の過程を証拠として残しておくことは非常に重要です。


意匠権を侵害された際の救済については、特許法とほとんど同様です。しかし意匠権の場合、不正行為による損害賠償請求の金額は意匠権者の実施能力に応じた額を超えない限度が設定されています。

商標権について
つづいて商標権についてです。

商標権とは事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービス(役務)を他人(他社)のものと区別するために使用するマークを保護する権利のこと。(出所表示、品質保証、宣伝広告など)法律上では、保護の対象を「文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合」したものを指すと規定されています。
商標権も同様に出願にすることによって権利が付与され、登録から10年間は独占的仕様が保護されます。そしてこの権利は更新申請が可能となっています。

商標権を取得要件としては、主に、その商標が、自分と他人の商品・サービスを区別するために使用できるのか(識別力)、公益に反する商標ではないか、他人の商標と紛らわしい商標ではないかという点で審査します。そして商標権の類似の判断にあたっては、商標の見た目「外観」・一般的な印象「観念」・読み方「称呼」の類似性の検討に加え、取引者や一般の需要者が商品購入時に通常払うと推測される注意の程度を基準として判断されます。
では、商標登録をせずに使用しているマークと類似したものが他人によって商標登録された場合どうなるのか?

この場合、商標登録の出願前から使用しており不正競争を目的としていないかつ、需要者に広く認識されている場合は、先使用権によって保護され、引き続き自己の商標を使うことが認められます。

著作権法について
最後は、前回に引き続き「著作権法」についてです。
著作権も知的財産の一種であり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった出願が必要な「産業財産権(工業所有権)」に対して、著作権は文化的な創作物を保護の対象としており、著作物を創作した時点で自動的に発生する権利です。

著作権が保護する対象は、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルにある人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物と呼ばれます。これらには芸術性の有無は関係なく、模倣やありふれた表現でなく創作的に表現されていれば保護の対象となります。著作権の保護対象には実用品や工業製品は該当しないが、逸品制作の美術工芸品や高度な美術性を有する場合は量産品でも該当するケースがあります。

前述したとおり、著作権は特別な手続きなしに著作物を創作した時点で自動的に権利が発生します。しかし例外として「職務著作」があげられます。職務著作とは、簡単に言うと会社に勤務している人が、会社の業務で著作物を作った場合は、その会社が「著作者」になり、その会社が「著作権」を保有すること。また、2人以上の者が共同して創作した著作物については、その各創作者の著作物に対する寄与を分離して個別的に利用することができないも場合は共同著作者となります。
では著作者はどのような権利が保護されるのか?


著作者は、著作物に対して独占的に「利用、処分」することができ、これには著作物の利用を許可し創作された二次的著作物も含まれます。これらの権利は個人の場合、本人が死亡した翌年の1月1日から70年間保護され、法人の場合、公表した翌年の1月1日から70年保護されます。
また、著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の二つに分かれます。著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり相続したりできないが、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続することができます。
つづいて、著作権の保護の制限についてお話しいただきました。著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができるように定められています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に決められています。 (写真参照)


つまり、著作権は、業務や営利目的ではなく私的利用に限定する場合や、調査研究や教育を目的に出所を明らかにしている場合、福祉や非営利活動で使用する場合、報道目的、立法・司法・行政上の理由で利用する場合、そして、美術の著作物の展示・譲渡など、文化を発展させることを目的としている場合には、必要に応じて著作権者に許諾を得なくても著作物の利用ができます。

今回のオンラインレクチャーでは、さまざまな判例をもとに崔氏の軽快なトークでクリエイターが本来知っておくべき法についてわかりやすく学ぶことができました。また、クリエイターとしての創作活動において、自分自身で作品や活動を守ることの大切さやきちんとした知識を蓄積していく重要さを改めて感じる時間となりました。